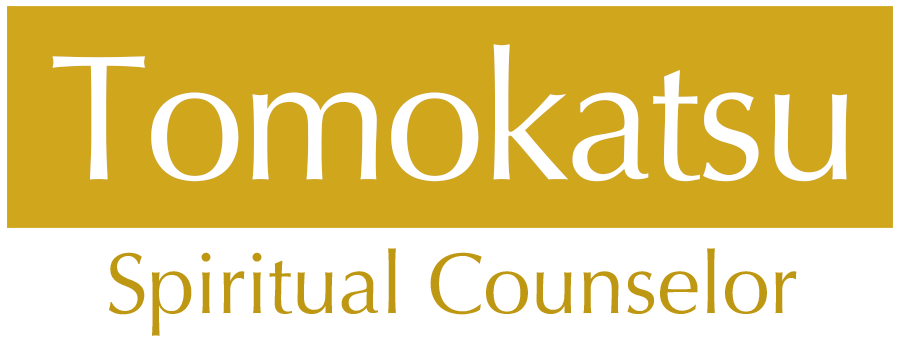スピリチュアルカウンセラーのTomokatsuです。
スピリチュアルだけでなく「自分軸を持とう」と言われる時代。
けれど「自分軸を大切に」と言われても、それがどういう状態なのか、どのように保てばいいのか、イメージが曖昧です。
そこで今回は、「自分軸」を保つための意識のプロセスとして、「輪郭を得た自己」と「あるがまま」という二つの在り方を比較しながら考えてみましょう。
意識の発達と自分軸の形成
実は、自分軸というものは「一度つくれば完成」というものではなく、人生の成長とともに、形を変えながら成熟していくものです。
その変化は、まるで芽が出て、茎を伸ばし、やがて花を咲かせるように、段階的に内面が広がりを見せていきます。ここでは、自分軸がどのように育っていくのか、三つの意識段階に分けて見ていきましょう。
1. 赤ちゃんの「無垢なあるがまま」
生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ“自分”と“他者”の区別もなく、ただ感じ、ただ存在しています。
この純粋無垢な状態は、「あるがまま」の原型とも言えるでしょう。ただし、そこにはまだ意識的な自分軸は存在しません。けれど、ひとつ確かなことがあります。
私たちは既に、生まれた瞬間のこの“あるがまま”を生きたことがあるのです。
それは無意識のうちの体験かもしれませんが、確かに私たちの中に残っています。だからこそ、知らないとは、もう言えないのです。
2. 成長する中での「輪郭を得た自己」
やがて私たちは、成長の過程で「自分」という感覚に目覚めていきます。
- これは好き
- それは違う
- 私にはこう見える など
周囲の世界との違いを感じ取りながら、意識の中に輪郭が少しずつ生まれていきます。
この段階では、「我を通す」というかたちで、自分の意思や価値観を表現することも増えてきます。ときにぶつかり、ときに拒まれながらも、「私はこう在りたい」という想いとともに、私たちはその意識の輪郭を確かめようとするのです。
この輪郭を得た自己の時期は、まだ柔らかく、不安定かもしれませんが、自分という存在が世界の中でかたちを持ち始める、大切なプロセスです。それは未熟さではなく、自分自身の軸を見出そうとする、健全で力強い試みと言えます。
3. 成熟の先にある「意識的なあるがまま」
ある段階に差しかかると、私たちは次第に、自己の輪郭にこだわりすぎることの苦しさに気づきます。具体的には「私らしさ」や「正しさ」を守ろうとするほど、他者との間に壁が生まれ、対立や孤立を招いたりする現実です。
その繰り返しのなかで、ふと力が抜ける瞬間が訪れます。
こだわらなくても、自分はここに在るという静かな気づきが、意識の奥に広がってくるのです。そこには、何かを主張するわけでも、押し通すわけでもない、けれど確かに「自分である」という感覚が宿っています。
この段階が、「意識的なあるがまま」で、自分の軸にしっかりと根を下ろしながらも、他者や世界とやわらかく響き合える在り方です。
「自分とは何か」を問い尽くした先にあらわれる、穏やかな統合の境地と言えるでしょう。
哲学・心理学から見た自分軸の形成
「自分軸は変化を通して成熟していくもの」である―
この見方は、心理学や哲学、仏教や道教の教えの中にも見られるのでしょうか?
その答えはYesです。自分軸が経験と変容を通じて育っていく、流動的で内的な軸であるということが様々な表現で伝えられています。
1. ユング:自我から自己への統合
カール・グスタフ・ユングは、自己とは単なる“自我(エゴ)”ではなく、より広く深い“自己(セルフ)”との統合によって成熟すると説きました。自己の影の側面や無意識と向き合うことで、自我中心の在り方を超えていくという考え方は、「輪郭を得た自己」から「意識的なあるがまま」への移行していく段階と一致します。
2. マズロー:承認欲求から自己実現への移行
アブラハム・マズローの欲求段階説では、人はまず外的な承認を求めますが、その後、内なる価値に従って自己実現を目指す段階へと進みます。これはまさに、我を通すプロセスを経て、自分の本質的な軸へと移行していく意識の成長を表しています。
3. 道教・仏教:無為自然・空・中道
道教の「無為自然」、仏教の「空」や「中道」といった考えは、こだわりや執着から離れた柔らかい在り方を示しており、穏やかな統合の境地である「意識的なあるがまま」の状態に向かうための思想です。
あるがまま=自分を捨てるという表現の危うさ
スピリチュアルでは、「あるがままに生きること」が「自分を捨てること」と表現されることがあります。しかしこの言葉を文字通りに受け取ってしまうと、自分を否定したり、感情を押し殺したりすることが「正しい在り方」であるかのように誤解される恐れがあります。
実際に私は、そうした状態に陥っている方々を目の当たりにし、その誤解をひとつひとつ解いてきました。
「あるがまま」とは、本来、自己を否定することではありません。
「あるがままに生きること」とは、過去にとらわれた自分像や、過度なこだわりといった、自我が固めた殻をやわらかくほどいていくプロセスなのです。
「捨てる」というよりも、「ゆるめる」とか「手放す」という言葉のほうが、その本質に、ずっと近いのです。
自然界に見る「あるがまま」の在り方
自分軸の目指すべき姿としている「あるがまま」は、自然界のいたるところに見出すことができます。
- 花は、咲くべき時に静かに咲き、やがて静かに散っていきます。
- 川は障害物を押しのけるのではなく、よけながら流れを変えていきます。
- 風は形に執着せず、空間に合わせて自在に吹き抜けていきます。
- 森の木々は空を取り合うことなく、それぞれに合った高さと広がりで、調和の中に在ります。
- 動物たちは他と比較することなく、ただ「そのように在る」ことに忠実です。
こうした存在たちは、誰かに見せるために生きているわけではありません。あるがままに在ることこそが、すでに調和であり、共生そのものなのです。
自然の「あるがまま」のお手本に触れることで、今必要な自分の内にある「あるがまま」の感覚を思い出すのかもしれません。
自分軸とは「通すもの」ではなく「気づくもの」
自分軸とは、「主張」や「正しさ」で押し通すものではありません。
「輪郭を得た自己」も、「意識的なあるがまま」も、どちらが優れているわけでも、間違っているわけでもありません。それぞれが必要な、通過すべき大切な段階です。
そしてその先に見えてくるのは、私で在りながら、私にこだわらないという自由な在り方。
まるで季節が静かに移ろうように。
川が障害を越えながら流れ続けるように。
風が、姿を変えながら空間を満たしていくように。
自然のお手本に触れつつ、私たちも自分の軸を保ちながら、しなやかに生きてみましょう。
YouTubeで解説した動画はこちら
今回のテーマをTomokatsu本人がライブ配信で解説しています。